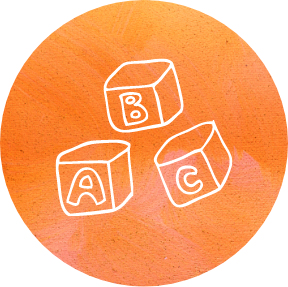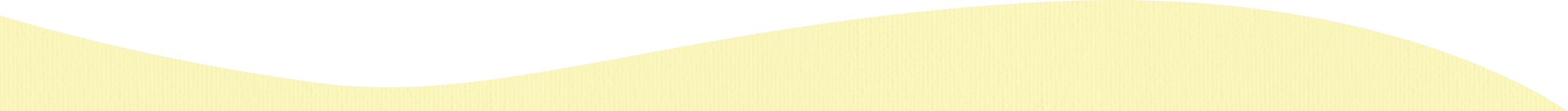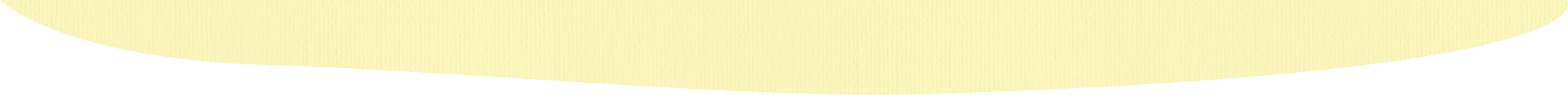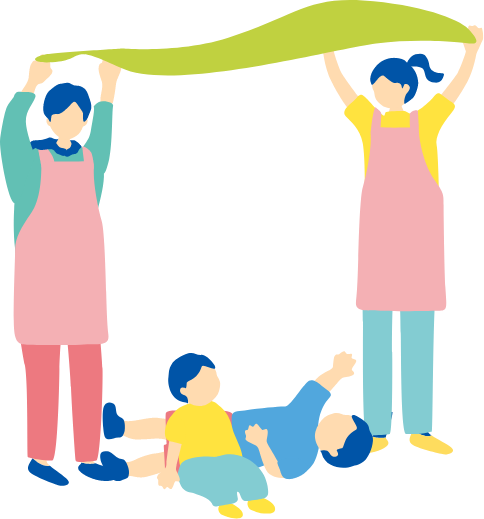Koko クラス
いろいろな人と関わり、さまざまな体験をする機会から、
学齢期、成人期の豊かな生活の基盤をつくります。

対象年齢:(児童発達支援)0歳~就学前(放課後等デイサービス)小学校低学年
たとえば…
・まだ自力での移動がむずかしい。
・肢体不自由と知的障がいが重複している。
・体調が安定してきて、お家以外で過ごす練習がしたい。
・学校生活に向けて、家族以外からのケアに慣れてほしい。
・同年代のお友達とふれあってほしい。
・長時間利用できる場所を探している。
同年代のこども同士の交流、遊びを通した発達支援を行っています。
月~金は送迎対応しております。昼食は持参です。
(対応可能な医療的ケアの内容)
人工呼吸器管理、気管切開管理、CV留置、酸素療法、経管栄養、人工肛門、導尿、痙攣時の処置 など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置:保育士、児童指導員、看護師、作業療法士、理学療法士
時間割
| 9:30 | 順次到着 健康観察、自由遊び |
| 10:00 | はじめの会 ふれあいあそび お散歩 |
| 12:00 | お昼ごはん |
| 13:00 | 午睡、食休み |
| 14:00 | 感覚あそび、体あそび |
| 15:30 | 帰りの準備、おわりの会 |
| 16:00 | 終了 |
※注入などはお子さまのリズムに合わせて随時対応します。
※昼食はお弁当持参です。
定員
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ||
| 10:00 – 16:00 | 児童発達支援 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | – | – | – |
| 13:30 – 16:30 | 放課後等デイサービス(小学生) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | – | – | – |
☆Kokoクラスの送迎について
月~金曜日は、送迎があります。
医療的ケアが必要なお子さまの場合は看護師が添乗します。
直線距離でおおむね片道5km圏内を通常の送迎範囲とさせていただいております。
5km地点:子安駅付近、西谷駅付近、上大岡駅付近、保土ヶ谷駅~東戸塚駅間、山手駅付近
【5km以上の範囲にお住まいの場合】
①途中のポイントで待ち合わせ
ご自宅以外でも、駅、バスポイント、公共施設の駐車場などで待ち合わせができます。
②5km以上の地点への送迎
曜日やお迎え時間をご相談させていただいた上で送迎可能な場合がございます。

Lala クラス
ひとりひとりの発達段階や特性に合わせて、
楽しく集団参加の基礎を育てます。

対象年齢:0歳~就学前(主に0~4歳)
たとえば…
・医療的ケアがあって、発達にも気になるところがある。
・小さく生まれた、入院が長かったなどで発達がゆっくりなため、促したい。
・ことばの遅れ・落ち着きのなさ・不器用さなどがあって発達支援を受けたい。
・就園に向けて、専門的な場所で集団参加の練習をしたい。
・親子で離れる練習をしたい。
医療的ケアがあっても利用できるクラスです。
発達の基礎となる感覚の凹凸を整え、発達のステップアップを促します。
(対応可能な医療的ケアの内容)
人工呼吸器管理、気管切開管理、CV留置、酸素療法、経管栄養、人工肛門、導尿、痙攣時の処置 など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置:保育士、児童指導員、看護師、作業療法士
時間割
| 9:00 | 健康観察 はじめの集会 |
| 9:20 | たいそう |
| 9:30 | 運動あそび、外出練習 |
| 10:30 | 机上活動、個別活動 |
| 11:30 | お昼ごはん |
| 12:00 | 午睡、食休み |
| 13:00 | 自発活動 |
| 13:45 | おわりの集会 |
| 14:00 | お迎え |
| 15:00までお預かり、または送迎 |
※必要な医療的ケアなどはその都度対応します。
※昼食はお弁当持参です。
定員
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
| 09:00 – 15:00 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | – | – |
Kai クラス
大きい集団では満たしきれない発達ニーズを補いながら、
その子らしく過ごせる時間を提供します。

対象年齢:0歳~就学前(主に4歳~就学前)
たとえば…
・運動、発達の遅れが気になる。
・感覚の過敏や鈍感さがある。
・幼稚園、保育園の集団活動で困っている。
・就学に向けてできることを増やしたい。
・自閉症スペクトラム、AD/HDなどの診断があり、
本人にあった支援を受けたい。(診断がなくても利用できます)
発達障がいがあるこども、発達がゆっくりなこどもの支援に特化したクラスです。
感覚統合の視点を取り入れた運動あそびや感覚あそびと、座って行う机上課題の2つの構成で、その子の発達に必要な刺激が受けられるよう促します。
(対応可能な医療的ケアの内容)
※2022年4月より、医療的ケアに対応いたします。
人工呼吸器管理、気管切開管理、CV留置、酸素療法、経管栄養、人工肛門、導尿、痙攣時の処置 など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置:保育士、児童指導員、看護師
時間割
| 16:00 | 健康観察 はじめの集会 |
| 16:10 | 運動あそび |
| 16:30 | 水分補給 |
| 16:35 | 感覚プログラム、制作活動、コミュニケーション活動 |
| 16:50 | おわりの集会 |
| 17:00 | お迎え |
定員
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
| 16:00 – 17:00 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | – | – | – |
※Kaiクラスは送迎がございません。
Liko クラス
在宅生活でも、その子らしく過ごせる時間を大切に、
ご本人とご家族が望む生活を実現するお手伝いをします。

対象年齢:0~18歳
たとえば…
・医療的ケアの内容や体調、肢体不自由などにより、外出することが難しい。
・通所に向けてリズムを作りたい。
・自宅でも遊びの時間を楽しみ、様々な経験をしてほしい。
(対応可能な医療的ケアの内容)*看護師が訪問の場合
人工呼吸器、気管切開、CV留置、酸素、経管栄養、人工肛門、導尿 など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置:看護師、児童指導員
時間割(一例)
| 13:00 | 健康観察 はじめの会 |
| 13:10 | たいそう |
| 13:20 | 運動あそび、体あそび |
| 13:40 | 水分補給、トイレ |
| 13:55 | 感覚プログラム、製作活動、コミュニケーション活動 |
| 14:00 | 自発活動 |
*プログラムの内容は、状態や体調に合わせて実施します。
定員
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
| 10:00 – 13:00 (うち1時間) |
● | ● | – | ● | ● | – | – | – |
| 14:00 – 17:00 (うち1時間) |
● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
※1回の訪問時間は45分~1時間です。訪問看護と連続してご利用いただく形もご相談ください。
Koko クラス
いろいろな人と関わり、さまざまな体験をする機会から、
学齢期、成人期の豊かな生活の基盤をつくります。

対象年齢
(児童発達⽀援)0歳〜就学前(放課後等デイサービス)⼩学校卒業年の3⽉末まで
定員
1⽇6名
送迎
往復あり
ルートによりお迎え時間は相談させていただきます。
対応可能な医療的ケアの内容
⼈⼯呼吸器管理、気管切開管理、CV留置、酸素療法、経管栄養、⼈⼯肛⾨、導尿、痙攣時の処置 など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置
保育⼠、児童指導員、看護師、リハビリ職(作業療法⼠、理学療法⼠、⾔語聴覚⼠等)
時間割(児童発達支援)
| 9:30 | 順次到着 健康観察 |
| 10:00 | はじめの会と、ふれあい遊び |
| 10:30 | 午前の活動プログラム、お散歩 |
| 12:00 | お昼ごはん |
| 13:00 | 午睡、食休み |
| 14:00 | 午後の活動プログラム |
| 15:15 | おわりの会 |
| 15:30 | 終了 |
※おれんじハウス戸塚保育園と併⽤の場合は上記の時間内で、ケアのスケジュールにあわせ て1時間〜利⽤できます。
※昼⾷は、おれんじハウス戸塚保育園と併⽤の場合は給⾷、児童発達⽀援のみの利⽤の場合 はお弁当持参です。
時間割(放課後等デイサービス)
| 下校時刻 | 学校にお迎え |
| 15:00 | 健康観察、はじめの会 |
| 15:30 | 活動プログラム |
| 16:45 | おわりの会 |
| 17:00 | 終了 |
※学校休業⽇は児童発達⽀援と同じ時間帯でのご利⽤となります。
Koko クラス
いろいろな人と関わり、さまざまな体験をする機会から、
学齢期、成人期の豊かな生活の基盤をつくります。

対象年齢
(児童発達⽀援)0歳〜就学前(放課後等デイサービス)⼩学校卒業年の3⽉末まで
定員
1⽇6名
送迎
往復あり
ルートによりお迎え時間は相談させていただきます。
対応可能な医療的ケアの内容
⼈⼯呼吸器管理、気管切開管理、CV留置、酸素療法、経管栄養、⼈⼯肛⾨、導尿、痙攣時の処置 など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置
保育⼠、児童指導員、看護師、リハビリ職(作業療法⼠、理学療法⼠、⾔語聴覚⼠等)
時間割(児童発達支援)
| 9:30 | 順次到着 健康観察 |
| 10:00 | はじめの会と、ふれあい遊び |
| 10:30 | 午前の活動プログラム、お散歩 |
| 12:00 | お昼ごはん |
| 13:00 | 午睡、食休み |
| 14:00 | 午後の活動プログラム |
| 15:15 | おわりの会 |
| 15:30 | 終了 |
※おれんじハウス⼆俣川駅前保育園と併⽤の場合は上記の時間内で、ケアのスケジュールにあわせ て1時間〜利⽤できます。
※昼⾷は、おれんじハウス⼆俣川駅前保育園と併⽤の場合は給⾷、児童発達⽀援のみの利⽤の場合 はお弁当持参です。
時間割(放課後等デイサービス)
| 下校時刻 | 学校にお迎え |
| 15:00 | 健康観察、はじめの会 |
| 15:30 | 活動プログラム |
| 16:45 | おわりの会 |
| 17:00 | 終了 |
※学校休業⽇は児童発達⽀援と同じ時間帯でのご利⽤となります。
Lala クラス
ひとりひとりの発達段階や特性に合わせて、
楽しく集団参加の基礎を育てます。

対象年齢
0歳〜就学前(主に年少まで)
定員
1⽇5名
送迎
⾏きのみ
ルートによりお迎え時間は相談させていただきます。
対応可能な医療的ケアの内容
⼈⼯呼吸器管理、気管切開管理、CV留置、酸素療法、経管栄養、⼈⼯肛⾨、導尿、痙攣時 の処置など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置
保育⼠、児童指導員、看護師、リハビリ職(作業療法⼠、理学療法⼠、⾔語聴覚⼠等)
時間割
| 9:30 | 順次到着、はじめの会 |
| 9:45 | 運動プログラム |
| 10:30 | 机上活動 |
| 11:00 | お昼ごはん |
| 12:00 | 午睡、⾷休み |
| 13:00 | 個別プログラム |
| 14:30 | 終了 |
※おれんじハウス戸塚保育園と併⽤の場合は9:30〜給⾷まで、または個別プログラムの時間 を利⽤できます。
※昼⾷は、おれんじハウス戸塚保育園と併⽤の場合は給⾷、児童発達⽀援のみの利⽤の場合 はお弁当持参です。
Lala クラス
ひとりひとりの発達段階や特性に合わせて、
楽しく集団参加の基礎を育てます。

対象年齢
0歳〜就学前(主に年少まで)
定員
1⽇5名
送迎
⾏きのみ
ルートによりお迎え時間は相談させていただきます。
対応可能な医療的ケアの内容
⼈⼯呼吸器管理、気管切開管理、CV留置、酸素療法、経管栄養、⼈⼯肛⾨、導尿、痙攣時 の処置など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置
保育⼠、児童指導員、看護師、リハビリ職(作業療法⼠、理学療法⼠、⾔語聴覚⼠等)
時間割
| 9:30 | 順次到着、はじめの会 |
| 9:45 | 運動プログラム |
| 10:30 | 机上活動 |
| 11:00 | お昼ごはん |
| 12:00 | 午睡、⾷休み |
| 13:00 | 個別プログラム |
| 14:30 | 終了 |
※おれんじハウス⼆俣川駅前保育園と併⽤の場合は9:30〜給⾷まで、または個別プログラムの時間 を利⽤できます。
※昼⾷は、おれんじハウス⼆俣川駅前保育園と併⽤の場合は給⾷、児童発達⽀援のみの利⽤の場合 はお弁当持参です。
Kai クラス
大きい集団では満たしきれない発達ニーズを補いながら、
その子らしく過ごせる時間を提供します。

対象年齢
0歳〜就学前(主に年少以降)
定員
1⽇5名
送迎
⾏きのみ
ルートによりお迎え時間は相談させていただきます。
対応可能な医療的ケアの内容
⼈⼯呼吸器管理、気管切開管理、CV留置、酸素療法、経管栄養、⼈⼯肛⾨、導尿、痙攣時 の処置など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置
保育⼠、児童指導員、看護師、リハビリ職(作業療法⼠、理学療法⼠、⾔語聴覚⼠等)
時間割
| 15:45 | 順次到着、はじめの会 |
| 16:00 | 運動プログラム |
| 16:30 | 机上活動 |
| 17:00 | 終了 |
※おれんじハウス戸塚保育園と併⽤の場合は15:45~17:00で利⽤できます。
Kai クラス
大きい集団では満たしきれない発達ニーズを補いながら、
その子らしく過ごせる時間を提供します。

対象年齢
0歳〜就学前(主に年少以降)
定員
1⽇5名
送迎
⾏きのみ
ルートによりお迎え時間は相談させていただきます。
対応可能な医療的ケアの内容
⼈⼯呼吸器管理、気管切開管理、CV留置、酸素療法、経管栄養、⼈⼯肛⾨、導尿、痙攣時 の処置など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置
保育⼠、児童指導員、看護師、リハビリ職(作業療法⼠、理学療法⼠、⾔語聴覚⼠等)
時間割
| 15:45 | 順次到着、はじめの会 |
| 16:00 | 運動プログラム |
| 16:30 | 机上活動 |
| 17:00 | 終了 |
※おれんじハウス二俣川駅前保育園と併⽤の場合は15:45~17:00で利⽤できます。
Liko クラス
在宅生活でも、その子らしく過ごせる時間を大切に、
ご本人とご家族が望む生活を実現するお手伝いをします。

対象年齢
0〜18歳
Kokoクラス、おれんじハウスこども訪問看護ステーションとの併⽤もご相談ください。
対応可能な医療的ケアの内容
⼈⼯呼吸器、気管切開、CV留置、酸素、経管栄養、⼈⼯肛⾨、導尿 など
上記以外のケア内容もお気軽にお問い合わせください。
配置
看護師、児童指導員、保育⼠
時間
10:00~17:00のうち1時間程度